GP名古屋2014 デッキ組みなおし
2014年4月27日 リミテッド コメント (4)
世間はニクスへの旅のプレリで盛り上がっていますね。
レポートが遅くなりましたがGP名古屋の締めくくりです。
GPの2日目はSSモダンに参加して4勝4敗1分けでした。
まだ、デッキのバランスが調整不足な上に
会場を見渡してメタゲームが僕の頭の中と大きくずれていました。
本番である8月のGP神戸に向けてモダンの練習もしなくては
では、本日の日記のテーマであるGP名古屋の反省について
右の画像3枚は入れるべきだった3枚です。
3枚目の画像を見て「?」と感じた方が多いと思いますが・・
僕の中での結論で
「今回のカードプールでは11枚目の平地を入れるべき」
と出ました。
このカードプールだと3ターン目に《威名の英雄》をプレイする事が1番多くなる勝ちパターンだからです。
《平地》11枚だと2ターン目に白ダブルシンボルの《ブリマーズの先兵》もかなり安定してプレイできます
GP名古屋の2週間前の美嶋屋GPTでは黒単をベースで組んだらかなり安定して黒ダブルシンボルのカードをプレイする事ができました。
http://nayazoo.diarynote.jp/201404042259288902/
《グリフィンの夢掴み》については、これだけの授与クリーチャーが入っていて《ヘリオッドの試練》まであるため《グリフィンの夢掴み》の能力は安定して誘発できGP名古屋本戦では毎試合、サイドからインしていました。
エンチャントに恵まれたプールで《グリフィンの夢掴み》をメイン採用しなかったのはミスでした。
まず、今回のGP名古屋でメインではこのデッキで登録するべきでした。
「白いカード」
1 《忠実なペガサス》
1 《ニクス生まれの盾の仲間》
1 《セテッサの戦神官》
1 《乗騎ペガサス》
1 《ブリマーズの先兵》
1 《ラゴンナ団の長老》
1 《威名の英雄》
1 《目ざといアルセイド》
1 《万戦の幻霊》
1 《グリフィンの夢掴み》
1 《ヘリオッドの試練》
1 《不屈の猛攻》
1 《剥離》
「青いカード」
1 《波濤砕きのトリトン》
1 《高巣の崇拝者》
2 《潮流の合唱者》
1 《理想の調停者》
1 《層雲歩み》
1 《保護色》
1 《突然の嵐》
1 《捕海》
「マルチカード」
1 《都市国家の神、エファラ》
「土地」
11 《平地》
6 《島》
白単タッチ青です。
《セテッサの戦神官》はカードパワーが弱いと判断しGP名古屋では使いませんでしたがこのカードを採用する事でほぼ単色をベースにする事ができます。
白単ベースにする事によって初手に《島》がなくてもキープする事ができます。
青マナを要求するクリーチャーは3マナの《波濤砕きのトリトン》からです。
初手に《平地》のみでキープした場合、3枚目の土地を引いた時に確立論通りだと《島》を1枚引いている事になりますが・・
「偏った引き」という事がおきた場合、3枚目の土地に《島》がこない事はおこりえます。
最悪、《波濤砕きのトリトン》は4ターン目からのアクションでも強いです。
基本的にこのデッキだと青いカードは4ターン目以降のプレイと考えます。
5マナダブルシンボルの《先見のキマイラ》を採用していないのも5枚目の土地を引いた時に確立論通りだと《島》を2枚引けるけれど「偏った引き」の時に青ダブルシンボルが出ないからです。
という訳で青のダブルシンボルは6マナの《理想の調停者》1枚のみです。
そもそも、
「ダイスに勝ったら後手」がセオリーだったミラディンの傷跡シールドの時の戦術を「ダイスに勝ったら先手」がセオリーのテーロスシールド環境に応用したのが間違いでした。
メインボードは
先手、後手のどちらでも丸く戦える白青で組むべきでした。
そして、サイド後先手の時にこちらに入れ替えます。
「白いカード」
1 《忠実なペガサス》
1 《ニクス生まれの盾の仲間》
1 《セテッサの戦神官》
1 《乗騎ペガサス》
1 《ブリマーズの先兵》
1 《ラゴンナ団の長老》
1 《威名の英雄》
1 《目ざといアルセイド》
1 《万戦の幻霊》
1 《グリフィンの夢掴み》
1 《ヘリオッドの試練》
1 《不屈の猛攻》
「赤いカード」
1 《無謀な歓楽者》
1 《常炎の幻霊》
1 《攻撃の元型》
1 《不機嫌なサイクロプス》
1 《鍛冶の神、パーフォロス》
1 《アクロスの徴兵人》
1 《稲妻の一撃》
1 《槌の一撃》
1 《恐るべき気質》
「マルチカード」
1 《アクロスの重装歩兵》
「土地」
11 《平地》
7 《山》
こちらが先手で押すデッキなので知人のアドバイスを参考に《剥離》は入れません。
GP名古屋本戦でボロスにしてしまった理由に僕の中で《恐るべき気質》の点数が高すぎるというのもあります。
ただ、このコモンカードは先手の時に本当に強いので先手ボロスでの明確な勝ち手段の1つです。
本戦でボロスを選択した理由で《稲妻の一撃》と《ケラノスの稲妻》の3点火力2枚体制がやりたかったのもありますが振り返ると、ここが反省点の1つになりました。
組みなおし後のボロスは赤のダブルシンボルのカードを《攻撃の元型》1枚に抑えました。
この先手ボロスのキープ基準として
2ターン目に《ブリマーズの先兵》をプレイできる、または3ターン目にを《威名の英雄》プレイできる初手なら《山》がなくてもキープはありえます。
ただ、そのキープをすると赤のダブルシンボルのカードが手札で腐るリスクが発生します。
《山》を2枚引いていない時に赤ダブルシンボルのカード2枚ともが手札にきてしまうと大きく不利なゲーム展開となるため赤のダブルシンボルは《攻撃の元型》1枚です。
《稲妻の一撃》と《槌の一撃》があり火力はすでに2枚入っているのでマナ基盤で無理して《ケラノスの稲妻》まで使う必要はありませんでした。
18枚目の土地が入っているのはこちらが先手なため1ターン目のドローがないからです。
1ターン目のドローがなくても安定して3~4ターン目まで土地を置きたいための土地18枚構成です。
デッキの安定性を上げるため《火花の衝撃》や《タイタンの力》といった戦術1のカードを序盤でプレイする考えもあるのですが
2ターン目で土地が止まり、相手本体に《火花の衝撃》をプレイ3枚目の土地を探しに行くような状況は弱いと思い18枚目の土地を入れるのが最適だと判断しました。
今回の日記に対して
「デッキ40枚中平地9~10枚構成でも高確率で序盤のターンで白ダブルシンボルのカードはプレイできる」といった反論は来そうです。
実際、
「40枚中10枚の土地でその色のダブルシンボルは2ターン目に出る」というのがセオリーとされています。
GP名古屋初日の全勝デッキを見てもそのマナ基盤理論でダブルシンボルのカードを序盤にプレイする事前提のデッキが何人かいます。
ただ、
「セオリーとされている色マナ枚数より1枚増やす事によってデッキの安定度を劇的に上げる事はできないか?」
というのが今回の僕の主張です。
今回のGP名古屋で強いカードプールを引き当てたにも関わらずに《ケラノスの稲妻》のカードパワーに惑わされてデッキのマナ基盤をいびつにしたのが敗因でした。
レポートが遅くなりましたがGP名古屋の締めくくりです。
GPの2日目はSSモダンに参加して4勝4敗1分けでした。
まだ、デッキのバランスが調整不足な上に
会場を見渡してメタゲームが僕の頭の中と大きくずれていました。
本番である8月のGP神戸に向けてモダンの練習もしなくては
では、本日の日記のテーマであるGP名古屋の反省について
右の画像3枚は入れるべきだった3枚です。
3枚目の画像を見て「?」と感じた方が多いと思いますが・・
僕の中での結論で
「今回のカードプールでは11枚目の平地を入れるべき」
と出ました。
このカードプールだと3ターン目に《威名の英雄》をプレイする事が1番多くなる勝ちパターンだからです。
《平地》11枚だと2ターン目に白ダブルシンボルの《ブリマーズの先兵》もかなり安定してプレイできます
GP名古屋の2週間前の美嶋屋GPTでは黒単をベースで組んだらかなり安定して黒ダブルシンボルのカードをプレイする事ができました。
http://nayazoo.diarynote.jp/201404042259288902/
《グリフィンの夢掴み》については、これだけの授与クリーチャーが入っていて《ヘリオッドの試練》まであるため《グリフィンの夢掴み》の能力は安定して誘発できGP名古屋本戦では毎試合、サイドからインしていました。
エンチャントに恵まれたプールで《グリフィンの夢掴み》をメイン採用しなかったのはミスでした。
まず、今回のGP名古屋でメインではこのデッキで登録するべきでした。
「白いカード」
1 《忠実なペガサス》
1 《ニクス生まれの盾の仲間》
1 《セテッサの戦神官》
1 《乗騎ペガサス》
1 《ブリマーズの先兵》
1 《ラゴンナ団の長老》
1 《威名の英雄》
1 《目ざといアルセイド》
1 《万戦の幻霊》
1 《グリフィンの夢掴み》
1 《ヘリオッドの試練》
1 《不屈の猛攻》
1 《剥離》
「青いカード」
1 《波濤砕きのトリトン》
1 《高巣の崇拝者》
2 《潮流の合唱者》
1 《理想の調停者》
1 《層雲歩み》
1 《保護色》
1 《突然の嵐》
1 《捕海》
「マルチカード」
1 《都市国家の神、エファラ》
「土地」
11 《平地》
6 《島》
白単タッチ青です。
《セテッサの戦神官》はカードパワーが弱いと判断しGP名古屋では使いませんでしたがこのカードを採用する事でほぼ単色をベースにする事ができます。
白単ベースにする事によって初手に《島》がなくてもキープする事ができます。
青マナを要求するクリーチャーは3マナの《波濤砕きのトリトン》からです。
初手に《平地》のみでキープした場合、3枚目の土地を引いた時に確立論通りだと《島》を1枚引いている事になりますが・・
「偏った引き」という事がおきた場合、3枚目の土地に《島》がこない事はおこりえます。
最悪、《波濤砕きのトリトン》は4ターン目からのアクションでも強いです。
基本的にこのデッキだと青いカードは4ターン目以降のプレイと考えます。
5マナダブルシンボルの《先見のキマイラ》を採用していないのも5枚目の土地を引いた時に確立論通りだと《島》を2枚引けるけれど「偏った引き」の時に青ダブルシンボルが出ないからです。
という訳で青のダブルシンボルは6マナの《理想の調停者》1枚のみです。
そもそも、
「ダイスに勝ったら後手」がセオリーだったミラディンの傷跡シールドの時の戦術を「ダイスに勝ったら先手」がセオリーのテーロスシールド環境に応用したのが間違いでした。
メインボードは
先手、後手のどちらでも丸く戦える白青で組むべきでした。
そして、サイド後先手の時にこちらに入れ替えます。
「白いカード」
1 《忠実なペガサス》
1 《ニクス生まれの盾の仲間》
1 《セテッサの戦神官》
1 《乗騎ペガサス》
1 《ブリマーズの先兵》
1 《ラゴンナ団の長老》
1 《威名の英雄》
1 《目ざといアルセイド》
1 《万戦の幻霊》
1 《グリフィンの夢掴み》
1 《ヘリオッドの試練》
1 《不屈の猛攻》
「赤いカード」
1 《無謀な歓楽者》
1 《常炎の幻霊》
1 《攻撃の元型》
1 《不機嫌なサイクロプス》
1 《鍛冶の神、パーフォロス》
1 《アクロスの徴兵人》
1 《稲妻の一撃》
1 《槌の一撃》
1 《恐るべき気質》
「マルチカード」
1 《アクロスの重装歩兵》
「土地」
11 《平地》
7 《山》
こちらが先手で押すデッキなので知人のアドバイスを参考に《剥離》は入れません。
GP名古屋本戦でボロスにしてしまった理由に僕の中で《恐るべき気質》の点数が高すぎるというのもあります。
ただ、このコモンカードは先手の時に本当に強いので先手ボロスでの明確な勝ち手段の1つです。
本戦でボロスを選択した理由で《稲妻の一撃》と《ケラノスの稲妻》の3点火力2枚体制がやりたかったのもありますが振り返ると、ここが反省点の1つになりました。
組みなおし後のボロスは赤のダブルシンボルのカードを《攻撃の元型》1枚に抑えました。
この先手ボロスのキープ基準として
2ターン目に《ブリマーズの先兵》をプレイできる、または3ターン目にを《威名の英雄》プレイできる初手なら《山》がなくてもキープはありえます。
ただ、そのキープをすると赤のダブルシンボルのカードが手札で腐るリスクが発生します。
《山》を2枚引いていない時に赤ダブルシンボルのカード2枚ともが手札にきてしまうと大きく不利なゲーム展開となるため赤のダブルシンボルは《攻撃の元型》1枚です。
《稲妻の一撃》と《槌の一撃》があり火力はすでに2枚入っているのでマナ基盤で無理して《ケラノスの稲妻》まで使う必要はありませんでした。
18枚目の土地が入っているのはこちらが先手なため1ターン目のドローがないからです。
1ターン目のドローがなくても安定して3~4ターン目まで土地を置きたいための土地18枚構成です。
デッキの安定性を上げるため《火花の衝撃》や《タイタンの力》といった戦術1のカードを序盤でプレイする考えもあるのですが
2ターン目で土地が止まり、相手本体に《火花の衝撃》をプレイ3枚目の土地を探しに行くような状況は弱いと思い18枚目の土地を入れるのが最適だと判断しました。
今回の日記に対して
「デッキ40枚中平地9~10枚構成でも高確率で序盤のターンで白ダブルシンボルのカードはプレイできる」といった反論は来そうです。
実際、
「40枚中10枚の土地でその色のダブルシンボルは2ターン目に出る」というのがセオリーとされています。
GP名古屋初日の全勝デッキを見てもそのマナ基盤理論でダブルシンボルのカードを序盤にプレイする事前提のデッキが何人かいます。
ただ、
「セオリーとされている色マナ枚数より1枚増やす事によってデッキの安定度を劇的に上げる事はできないか?」
というのが今回の僕の主張です。
今回のGP名古屋で強いカードプールを引き当てたにも関わらずに《ケラノスの稲妻》のカードパワーに惑わされてデッキのマナ基盤をいびつにしたのが敗因でした。


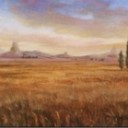

コメント
>ただ、「セオリーとされている色マナ枚数より1枚増やす事によってデッキの安定度を劇的に上げる事はできないか?」というのが今回の僕の主張です。
実際に計算すると《平地/Plains(THS)》を10枚から11枚にした場合2t目にWWを確保できる確率は66%程度から72%程度に上昇するのみなので、1枚増やしたからと言って「劇的に安定する」とは言い難いと思うのですがいかがでしょうか。
個人的には実際に計算してみると、メインカラーとは言え色拘束の極端に高いカードは相応の強さがないと採用を考えるべきである、と言うのと期待値としては2t目にWWが欲しければ《平地/Plains(THS)》10枚で良いが確率的には66%程度であると認識する必要があると言うのが妥当な言かと思いました。
>確率は66%程度から72%程度に上昇するのみ
この数字をどう捉えるかは人それぞれですが、確立が6%も上昇しているのなら僕としてはやる意味はあると考えます。
よく、この環境でダブルシンボルのカードがプレイできずに負けたという話は聞くのでダブルシンボルのカードをデッキに多く取るリスクは考えるべきだと思います。
スライ信者さんは
>ただ、「セオリーとされている色マナ枚数より1枚増やす事によってデッキの安定度を劇的に上げる事はできないか?」というのが今回の僕の主張です。
と言われるので、1枚増やした時に「劇的」には変化しないと言いたいのです。
実際に計算すると平地を8枚入れた場合は2t目にWWが確保できる確率は51%程度、9枚では59%程度、10枚入れた時は66%程度、11枚入れた場合は72%程度で10枚から11枚の場合のみ特別な変化が起こると言う事はありませんよね?
どう言う点で「セオリーとされている色マナ枚数より1枚増やす事によってデッキの安定度を劇的に上げる事はできないか?」と御主張されるんでしょうか。
僕の方でも説明が足りていない所がありましたが
1枚増やす毎に安定して2ターン目にダブルシンボルを出せる確立が6~8パーセントずつ増えていくのはその通りで10と11枚の間だけ上昇率が違うというのは起こりませんね。
僕が言いたかったのは
「2、3ターン目にダブルシンボルのカードをプレイしたいのなら40枚中10枚がセオリーと言われているが、実際にGP名古屋でその構築をしたら何度か事故で落としたセットがあったため1枚多目の11枚にした方がよいのでは?」
とそういった疑問です。